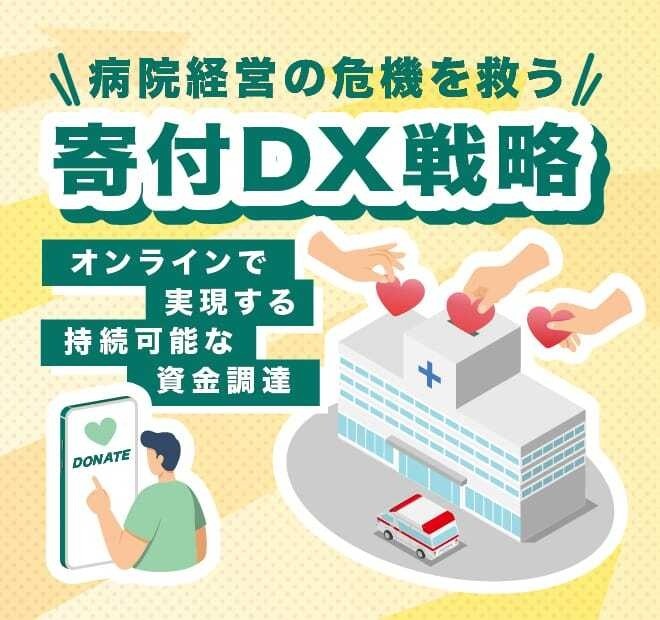厚労省 医師・看護師等の働き方ビジョン検討会のポイント紹介!

今月の厚労省要約コラムは、≪新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会≫(以下本検討会)についてです。
本検討会は、2016年10月3日に始動し2017年4月6日に一応の結論を得ました。目的として経済・人口動態の変化に対応出来なくなった日本の医療・介護サービス体制を将来に適した構造に変えていく手法を導くためのものです。
本検討会では、4つの論点があります。
-
1.「地域で市民と患者の生活を支える」
-
2.「専門性の追求と人生の選択の両立」
-
3.「生産性と質の向上」
-
4.「経済活力(イノベーション・国際化)への貢献」
これらに基づき議論をしています。
その際に
-
1.能力と意欲を最大限発揮できるキャリアと働き方をフル・サポートする
-
2.地域の主導により、医療・介護人材を育み、住民の生活を支える
-
3.高い生産性と付加価値を生み出す
上記の3つのビジョンが提示されました。
本テーマのコラムは3部構成となっており、主に検討会で決定したビジョンと具体的内容についてご紹介します。
第1部となる記事では、「能力と意欲を最大限発揮できるキャリアと働き方をフル・サポートする」ビジョンについてです。
目次
1.第1部の論点
2.「能力と意欲を最大限発揮できるキャリアと働き方をフル・サポートする」の内容について
第1部の論点
近年の高齢者人口増加による患者構造の変化によって、将来発生するであろう医療従事者の働き方の変化と人材確保の困難さについて議論されています。
社会保障・税一体改革の試算によると看護職員は2025年までに約200万人必要ですが、現状のペースで進むと約3万人から13万人の不足が予想されています。
その結果、医療従事者の負担増という課題が明確になり、離職率の増加につながるのではと懸念されています。
また地域偏在、高齢者医師や女性医師の増加などの課題が浮き彫りになっています。
それらの早急な具体的対策を検討する必要がありました。
そこで本検討会では、様々な分野の有識者や構成員によってそれらの問題の根本原因の追究、問題解決のための対策を議論した結果、「能力と意欲を最大限発揮できるキャリアと働き方をフル・サポートする」というビジョンが提示されました。
次に、ビジョンを実現するための具体的方策を見ていきましょう。
「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」の要点のご紹介
このビジョンでは、医療従事者にとって良いキャリア形成と柔軟な働き方をサポートするためには、どのようなことをしていくべきかを提示しています。それではじっくりと見ていくため、以下に具体的方策の概要を記載します。
-
①個々の医療機関の人材・労務マネジメント体制の確立と支援等
-
-
・画一的な規則で医療機関の人材・労務マネジメント体制を構築するのではなく、
-
個々の医療機関の状況に応じて構築していきましょう。
-
-
・マネジメント能力を育成するため、研修に参加したりスタッフ配置を
-
考慮したりしましょう。
-
・医療従事者の状況に即した働き方制度を確立しましょう。一例を挙げると家族の育児・介護
-
等の負担を担う者には、柔軟な短時間労働制度、時差勤務制度の導入や兼業、在宅労働、
-
施設内保育所の整備等の工夫を支援する必要があります。
-
・医療従事者のキャリア形成をより良いものにするため、個々人の具体的的目標を含めた
-
キャリア・アップ・カリキュラムの作成やそれをサポートする組織的体制を
-
確立しましょう。
-
②女性医師支援の重点的な強化
-
・近年の女性医師増加による、女性医師の働き方の見直しです。特に出産・育児などの
-
ライフイベントでどのような支援ができるかと考えた時に、柔軟な短時間労働制度、
-
時差勤務制度の導入や兼業はもちろんの事ですが
-
他業界で実践されている女性の働き方のノウハウを医療業界用に当てはめて
-
導入を検討しましょう。
-
・医師という「男性社会」の中、女性医師は女性ならではの悩みなどを相談する
-
相手がいないという問題があります。そこでキャリア、働き方、人生設計等の
-
漠然とした不安や疑問にも対応できるワン・ストップの相談機能やメンターの設置等の
-
取組みも求められます。
-
③地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援センターの実効性の向上
-
・各都道府県に設置されているものの、上手に活用されていないのが現状です。
-
今後の役割を果たすためまずは認知度の向上のための
-
マーケティング活動に尽力しましょう。
-
認知度が向上したら個別の医療機関の取組みの課題事例や成功事例を情報収集して
-
大学病院や地域の医療機関、学会等と協働して分析・検討すること、
-
第三者的な評価を行うこと、良い取組みを行う医療機関を表彰すること、
-
また、労務管理や人材マネジメントに関する講習を行ったり、
-
講師の派遣を仲介したりすること等の方策が考えられます。
-
④医師の柔軟なキャリア選択と専門性の追求を両立できる研修の在り方
-
・医療従事者はプロフェッショナルとしての目標の高いキャリア形成を望んでいます。
-
ですから個々人のキャリアビジョンを実現できるような環境を整えましょう。
-
医師の場合は臨床実習、臨床研修、専門研修などの過程で
-
個々のキャリア形成に適した選択できたり、
-
十分な経験をできる研修場所を提供する環境です。
-
またキャリア形成の妨げになる出産・育児・介護などに対応するため
-
再度研修を受講できる環境も必要です。
-
⑤看護師のキャリアの複線化・多様化
-
・看護師においてもより良いキャリア形成ができるようにすべきです。
-
また、看護師の働き方も変革していく必要があります。どういうことかと言うと、
-
高齢化人口の増加により従来の急性期中心の診察を補助する業務から
-
慢性期・回復期の診察を補助する業務や地域包括ケアシステムの構築による
-
将来医療の在り方変化による働き方の転換があります。
-
そういった背景により、看護師の多様化に対応できる
-
複数の養成システムを維持・発展する必要があります。
-
・看護師の働き方について興味深いプレゼンが広島大学の森山参考人からありましたので
-
紹介すると、看護師の働き方を海外比較したものとなっています。
-
海外の看護師は在宅ケアに注力していたり、
-
医師の業務負担を減らすため業務移譲を行っていることが分かります。
-
詳細はこちら。
-
⑥医療・介護の潜在スキルのシェアリング促進
-
・我が国の医療・介護従事者は非常に貴重です。少子高齢化による労働力の減少の中で
-
医療・介護従事者の不足を防ぐ必要があります。
-
そこで、リタイア人材を再登用できるシステムを構築して医療・介護人材の負担を
-
軽減したいのです。
-
そのため、一度退職した医療・介護従事者人材の経験や知恵を有効に活用できる
-
「医療・介護従事者シェアリング・バンク」(仮称)の整備が求められます。
-
柔軟な勤務形態を実現でき、身体的精神的に
-
負担が少ない業務に退職後の医師を紹介・派遣が出来ます。
-
また病児保育、民生委員、児童委員、保護司等に退職後の
-
医師・ 看護師・介護福祉士・社会福祉士等を紹介・派遣したりすること可能です。
-
また、上記について済生会横浜市東部病院の熊谷構成員のプレゼンがありましたので
-
ご紹介すると、タスクシフティングとタスクシェアリングの推進を
-
日本の現状と海外との比較を用いたり日本での成功事例を含めながら説明しています。
-
詳細はこちら。
参考文献
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000161081.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000146855.pdf
まとめ
ここまでいかがでしたか。
本検討会は、日本の経済・人口動態が大きく変化することが予想される中、医療の在り方も大きく変化するのに対してどのような対応をしていくべきかを提示しています。
今回は医療・介護従事者に焦点をあてた対応策をご紹介しました。
医療・介護従事者のキャリア形成や働き方を将来に適した形にするため、今後は変革の流れが出てくるでしょう。